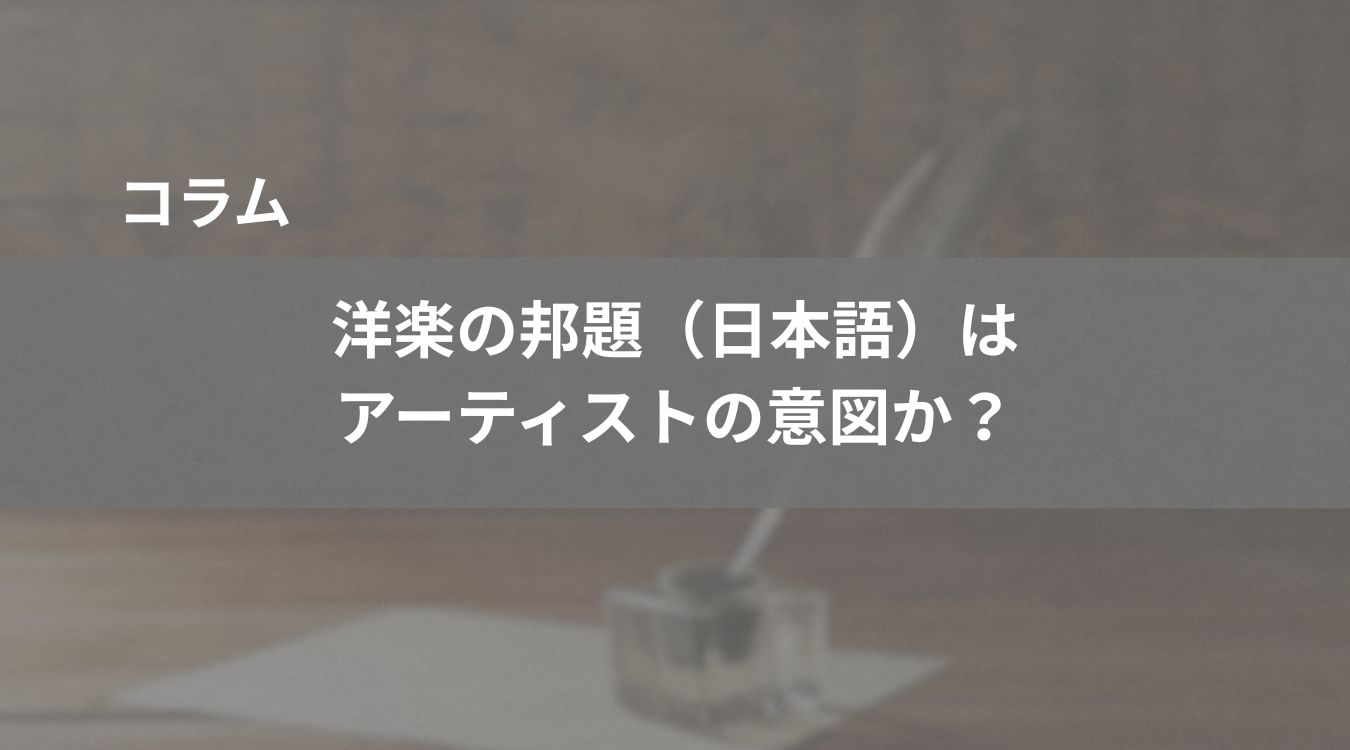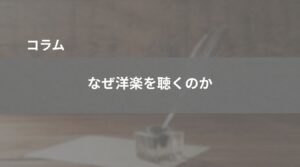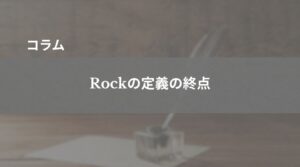洋楽の邦題(日本語訳)の問題
主に1980年代以前の洋楽には、アーティストが決めた原題とは別に、日本市場のための「邦題(日本語訳)」が付けられる文化がありました。
たとえば、ビートルズには「抱きしめたい(邦題)」という有名な楽曲があります。
「抱きしめたい」の原題は『I Want to Hold Your Hand』。つまり「手を握りたい」です。このタイトルでは、恋が始まる青春のような「初々しさ」や「ときめき」が上手に表現されています。
ところが、日本で付けられた邦題「抱きしめたい」は、よりストレートで強く、大人風なニュアンスに変わっています。確かに「抱きしめたい」は短くてインパクトがあり、邦題としては悪くないのかもしれません。
しかし、アーティストの作品の印象を変えてしまうかもしれない「邦題」は、どのように決められているのでしょう。
邦題は誰が決めているのか
実は、「邦題」はアーティストの意図によるものではありません。許可を取る必要もなく、事前に連絡する義務すらないのです。
つまり、日本でリリースされた自身の作品タイトルを見て、アーティスト本人が初めて「邦題」の存在を知るというケースも、普通に起こり得るのです。
では、いったい誰が邦題を決めているのでしょうか?
その答えは、楽曲の販売権を持つレーベルです。邦題は、その販売戦略に基づいて、レーベルが独自に決定しているのです。
「ヒドイお話」・・ではありません。販売数を最大化することが目的のレーベルにとっては、キャッチーで分かりやすい邦題をつけること自体が、重要なマーケティング戦略なのです。
アーティストとレーベルの間には、表現者と商業者という「大人の問題」が潜んでいるのです。
実例:作品の世界観を壊してしまった邦題たち
ブルース・スプリングスティーン:Thunder Road
- 原題:Thunder Road
- 邦題:涙のサンダーロード
ブルース・スプリングスティーンの名盤『Born to Run』の冒頭を飾るThunder Roadは、若者が夢と愛を胸に夜のハイウェイを駆け抜ける、疾走感あふれるロックナンバーです。
この曲に与えられた邦題が「涙のサンダー・ロード」。
無骨でストレートなアメリカン・ロックが、“涙の”という情緒的でワザとらしい装飾によって、印象を大きく損ねてしまいました。
ケイト・ブッシュ:The Kick Inside
- 原題:The Kick Inside
- 邦題:天使と小悪魔
ケイト・ブッシュのデビュー作『The Kick Inside』は、内側からのキック、つまり「胎動」を意味しています。そして同名の楽曲では近親愛の末に身籠った少女の繊細で悲劇的な心情が歌われています。
しかし邦題は「天使と小悪魔」。
本来、作品に向けられるべきタイトルが、神秘的な新人歌手(ケイト・ブッシュ)を印象づける言葉へとすり替えられたことで、作品の本質である「女性の目覚め」や「生と死の境界」といった重いテーマが隠蔽されてしまいました。
アーティストの世界観を、安易なイメージで壊してしまった典型例です。
キャロル・キング:You’ve Got a Friend
- 原題:You’ve Got a Friend
- 邦題:君のともだち
キャロル・キングの名曲『You’ve Got a Friend』は、「思い出して。あなたにはいつでも寄り添う友だちがいるから。」という、相手を主体にした優しい楽曲です。
ところが邦題では「(私は)君のともだち」と、主体が“わたし”に入れ替わった印象があり、どこか押しつけがましいタイトルになりました。また、「君のともだち」という言葉の響きには、幼児番組の主題歌のような、やや幼さや軽さも感じられます。
英語のニュアンスをそのまま日本語に訳すことは難しいです。それでもこの邦題は、アーティストの意図や、作品の持つ雰囲気を損ねてしまった例と言えるでしょう。
実例:原曲の魅力を損なわなかった優れた邦題
ポリス:Every Breath You Take
- 原題:Every Breath You Take
- 邦題:見つめていたい
原題はやや長く、直訳してしまうと「あなたのすべての呼吸」となり、好意を超えた“歪んだ愛情”すら感じさせます。そこを『見つめていたい』と、ロマンティックな余韻を印象付けた邦題は見事です。
ビージース:First of May
- 原題:First of May
- 邦題:若葉のころ
直訳すると「5月1日」。幼き日の初夏を懐古するこの楽曲には、『若葉のころ』という詩情豊かな邦題が名付けられました。
ポール・モーリア:L’amour est bleu
- 原題:L’amour est bleu
- 邦題:恋はみずいろ
直訳すると「愛は青い」。「愛」を『恋』に変えたことで淡い印象に。そして「青」が持つ強さや冷淡なイメージを『みずいろ』に和らげた表現は秀逸です。
あとがき(洋楽の邦題)
洋楽の邦題を目にして、「あれ?」や「なぜ?」と違和感を覚えたこと。それが、この記事をご覧になったきっかけだったかもしれません。
本文でも触れたとおり、邦題は必ずしもアーティストの意図に基づいているわけではなく、多くはレーベル側の戦略によって独自に命名されてきました。
おそらく、1970年代から90年代のあいだに、日本人の平均的な英語力は大きく向上し、多くの人がある程度の原題を理解できるようになりました。その結果として、洋楽に邦題を付ける習慣は次第に薄れ、90年代以降は「原題そのまま」の傾向が強まったように感じられます。
とはいえ、過去の名盤に触れるとき、「邦題」の存在は避けて通れません。
もし、その作品に込められたアーティストの思いやメッセージを純粋に受け取りたいと思うなら。ぜひ『原題だけが、アーティスト自身の言葉』である。
そのことを心に留めて、名盤を再生してください。