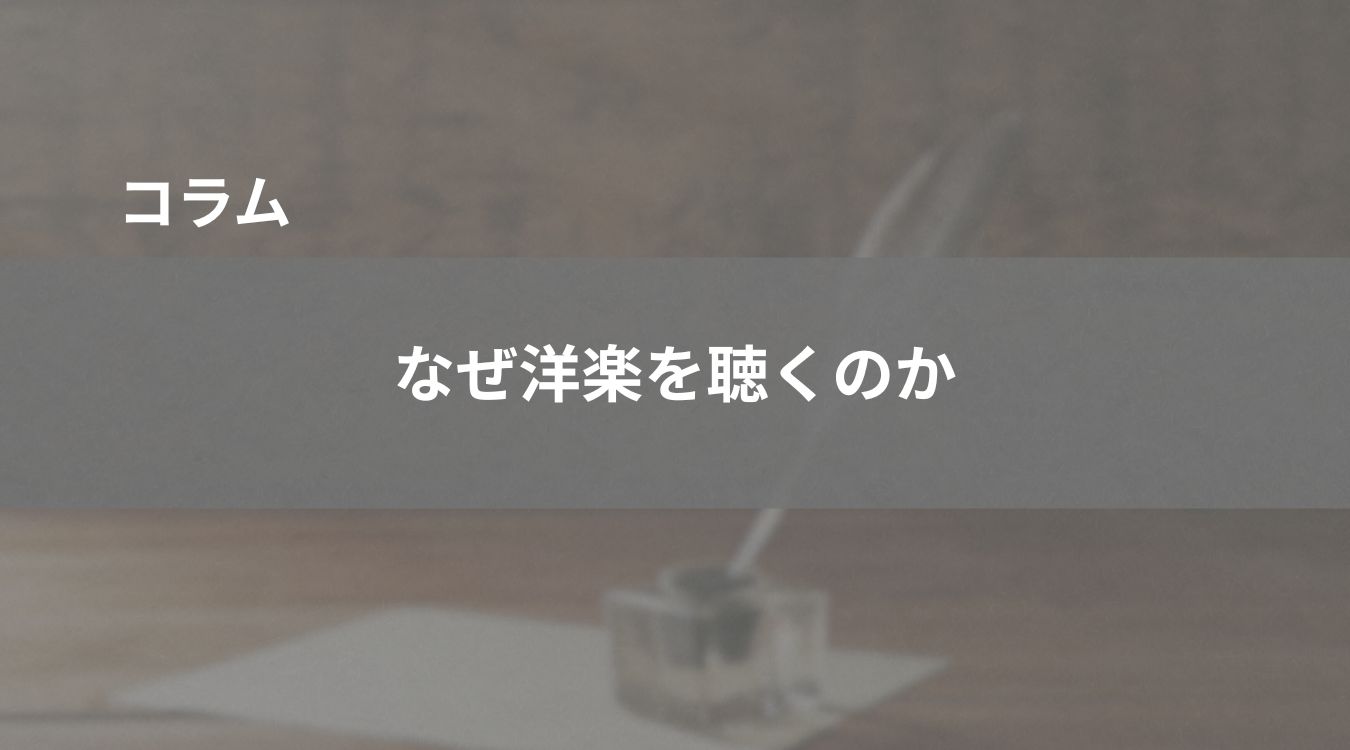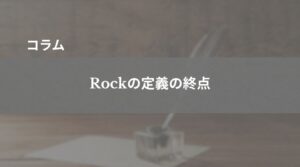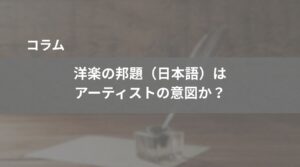「特別感」を帯びる洋楽派
音楽を聴くことが多いリスナーは、だいたいの場合「邦楽派」と「洋楽派」に大別されます。もちろん、楽曲の原産国を意識せずに音楽を楽しむリスナーも存在します。
ただし、邦楽派と洋楽派、それぞれに強く傾いている者同士では、『音楽』という共通の趣味を持ちながら、音楽をテーマに会話し、共感し合うことは困難です。そして、「洋楽しか聴かない」ことを公言する人に対しては、どこか「特別な感じ」を自演しているように感じるかもしれません。
あえて自国以外の音楽しか聴かない“洋楽リスナー”は、「人と違う自分」に陶酔するために洋楽を聴いているのか。
この記事は、「洋楽リスナーはなぜ洋楽を聴くのか」について多面的に論考し、その嗜好性について合理的な終点を見出すことを目的にしています。
なぜ洋楽を聴くのか
洋楽リスナーが洋楽を選ぶ理由は、多くの場合、「人と違う自分を演出したい」という単純なものではありません。
その背景には音楽そのものの成り立ちや歴史、さらには身体に作用するリズムの違いなど、文化的にも生理的にも深い要素が存在しています。
邦楽ファンからすれば、最も大きな疑問は「歌詞の意味が分からないのに、面白いのか」という点かもしれません。言葉の理解を重視する立場からすると、確かに不可解に映る選択です。
しかし実際には、日本人が洋楽を聴く理由は、その素直な疑問を超えたところにあります。
邦楽ファンであっても、「Let It Be」や「Yesterday Once More」のように、時代を超えて愛される洋楽の名曲を耳にしたことはあるでしょう。その完成度や普遍的なメロディは、国境を越えて心に届く力を持っています。
つまり、歌詞を理解できなくても、洋楽には「何か特別な魅力があるのではないか」という疑問が成立するのです。
なぜ洋楽を聴くのか。終点まではもう少し本質を掘り下げる必要がありそうです。
音楽的基盤の差異
日本のポピュラー音楽と欧米のポピュラー音楽は、その成り立ちの時点から大きな違いを抱えています。
日本のポピュラー音楽は、戦後のテレビやラジオといったメディアの普及とともに広がりました。音楽は番組や流行と結びつき、娯楽産業の一部として制度化されていきました。
つまり、多くの人にとって音楽は「日常を彩るもの」「流行に乗るもの」として身近になったのです。
一方で、欧米のポピュラー音楽は、ブルースを源流としています。ブルースは黒人奴隷制度という過酷な社会的背景から生まれ、抑圧ややるせなさを直接的に表現するための手段でした。
音楽は娯楽である前に「生存の表現」であり、感情や衝動を吐き出す切実な営みだったのです。そこからジャズやロックンロール、ソウル、ヒップホップへと受け継がれていきました。
こうした基盤の違いは、音楽の「寿命」にも表れています。
たとえば1960〜70年代に生まれた洋楽の数々は、いまもなお世代を超えて聴き継がれています。ビートルズやローリング・ストーンズ、レッド・ツェッペリンといった名前は、当時を知らない若い世代にとっても身近な存在となっています。
対して、同時期の邦楽はごく一部を除けば、現在の若い世代にまで広く聴き継がれているとは言い難いのが現実です。
これは単に優劣の問題ではありません。音楽が育った基盤そのものの違いが、その「持続性」や「普遍性」に影響を及ぼしているのです。
娯楽産業の流行サイクルに依存した邦楽と、衝動の表現から始まった洋楽。その差異が、今日に至るまでの存在感の違いとして現れていると考えられます。
つまり、日本人が洋楽を聴くのは、単なる国際的な流行の消費ではなく、自国の音楽では触れにくい「衝動の密度」や「表現の普遍性」、そして「ポピュラー音楽の原点」に触れる体験なのです。
音楽の身体的な同期
邦楽ファンが洋楽リスナーに対して抱く最大の疑問のひとつに、「歌詞の意味が分からないのに、なぜ面白いのか」というものがあります。この問いに対する大きな手がかりが、音楽の持つ“身体的な同期”です。
欧米のポピュラー音楽の多くは、ブルースやR&Bを起点に発展しました。これらの音楽は、リズムの「揺れ」や「繰り返し」を通じて、聴き手の身体に直接作用する特徴を持っています。
いわゆる「グルーヴ感」や「ノリ」と呼ばれるものは、意味や言語を超えて、体が自然に動き出してしまうような感覚を生み出します。さらに、身体性は楽器編成や演奏文化の違いにも支えられてきました。
洋楽では1960年代以降、ピアノやオルガン、さらにはシンセサイザーが積極的に導入され、ドラムやベースとともにリズムを前面に押し出すバンド・アンサンブルが一般的になりました。4〜5人組のバンド編成が主流となり、それぞれの楽器が「音を重ねる」のではなく、「リズムを掛け合わせる」役割を担ったのです。
一方、日本のポピュラー音楽は、同時期にはアイドル歌手や歌謡曲の全盛期であり、バック演奏はスタジオミュージシャンが整えた伴奏に依存するケースが多く見られました。
3人組のユニットやソロ歌手が前面に立ち、歌声と歌詞を主軸に据える声楽的構造です。楽器の生演奏よりも「メロディと歌詞の分かりやすさ」が優先されたため、リズムによる身体的な巻き込みは相対的に弱かったといえます。
つまり、洋楽を聴くという行為は、歌詞を理解するという知的プロセスよりも前に、バンドのアンサンブルやリズムのうねりそのものに身体や感情が同期する体験を意味しています。
邦楽が歌詞やメロディを介して心情を届けてきたのに対し、洋楽はバンド文化を背景に、言語を超えたリズムの快楽を提示してきました。歌詞が分からなくても楽しめるのは、その身体性が根底にあるからなのです。
日本アニメの海外受容
日本人が洋楽を聴く理由を理解するには、日本アニメを楽しむ海外のファンの存在を考えると分かりやすいでしょう。
欧米をはじめ世界各地には、自国にもアニメーション文化があるにもかかわらず、日本のアニメに強く惹かれる人々が数多く存在します。そこには、欧米作品には見られない作画のタッチや物語の構造、感情表現の方法といった独自の文化的基盤があります。
つまり、海外のファンが日本アニメを選ぶのは「外国の作品だから」ではなく、自国の作品では得られない表現や感覚に魅力を感じるからです。この嗜好はごく自然な現象であり、異文化消費というよりも「異なる文化的基盤に触れたい」という欲求の表れにすぎません。
この構造は、日本人が洋楽を聴く理由と同じです。
私たちが米英の音楽に魅力を感じるのも、単に海外文化への憧れではなく、邦楽では触れにくい衝動の密度やリズムの身体性を味わいたいからなのです。
日本アニメが海外で受容されている現象を参照すれば、「なぜ日本人が洋楽を聴くのか」という問いも理解しやすくなります。どちらも、自国には存在しない文化の基盤に魅力を見いだす、至って正常な嗜好の現れなのです。
終点(音楽嗜好に宿る偏見)
ここまで、日本人が洋楽を聴く理由について、歴史的背景や文化的基盤の差異をもとに考えてきました。
その過程では、どうしても「洋楽の方が優れている」と読めてしまう部分があったかもしれません。しかし本質的に音楽は、国境や優劣を意識して聴くものではありません。
確かに1960〜70年代という時代を切り取れば、欧米の音楽は「衝動の表現」としての密度を持ち、日本のポピュラー音楽とは成り立ちの面で大きな差異がありました。
しかし、その構造が永遠に固定されているわけではありません。
情報の国際化が進んだ1980年代以降、日本のミュージシャンは積極的に洋楽から学び、吸収し、新しい表現を形にしてきました。シティポップの再評価や、ロック、ヒップホップの国内展開はその象徴といえるでしょう。
今日の日本の音楽シーンには、洋楽の影響を取り込みながらも独自の感性を打ち出すアーティストが数多く存在しています。
音楽嗜好には「洋楽こそ本物」「邦楽は軽い」といった偏見がつきまといがちです。
しかし、音楽の価値を決めるのは国籍ではなく、その表現がどれだけ聴き手に作用するかという一点に尽きます。洋楽に特別感を抱くのも自然な感覚ですが、それを偏見に変えてしまうと、本来の楽しみを狭めてしまいます。
結局のところ、私たちが音楽に惹かれる理由は、歴史や文化の違いを踏まえつつも、最終的には「心や身体を動かす力」にあります。邦楽であれ洋楽であれ、その魅力をどう受け取り、どう楽しむかはリスナー自身に委ねられているのです。