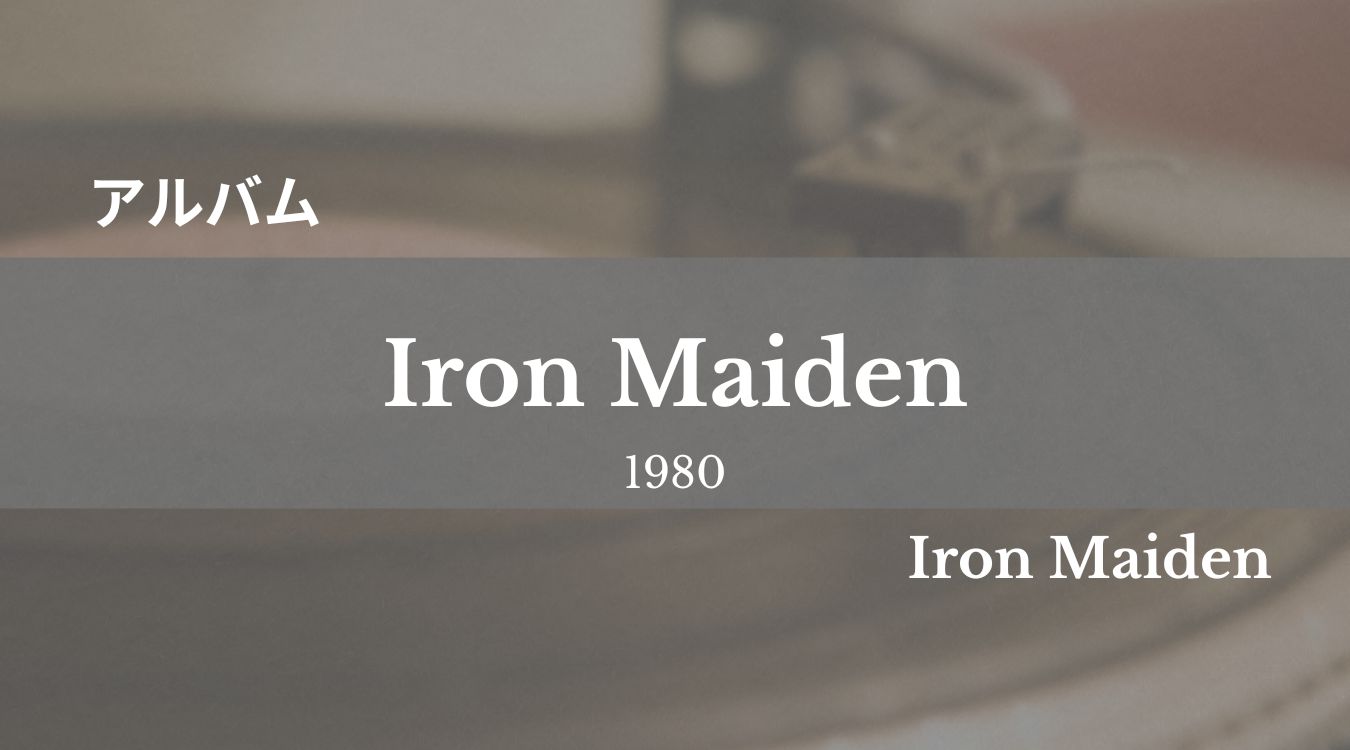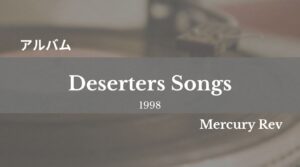当サイトの評価
[★★★☆]
- 1stアルバム
- リリース_1980年
- 作品名_Iron Maiden(邦題:鋼鉄の処女)
Spotify
Apple Music
NWOBHMの幕開けを告げた代表的名盤
本作Iron Maidenは、後の大英帝国的スケールの“メイデン像”が形成される前夜に、サウンドの方向性を一挙に提示したアルバムです。
バンドリーダーのスティーブ・ハリスの疾走感あるベース、ツインギターの対位法、ストリート出身の荒々しい声質。そして、1曲の中で複数の楽章的パートを切り替えて、短い組曲のように展開していくミニ・スイート的な構造がすでに完成していました。
そして、アイアン・メイデンのマスコット的存在の「エディ」も本作から登場しています。
ジャケットに描かれた骸骨的のような「エディ」は、以後、すべてのスタジオ・アルバムや多くのシングルに描かれ続け、その時代の音楽テーマや時代背景を象徴する姿に変化して登場します。
本作で描かれているのは、夜のロンドンの裏路地に立つエディ。1980年前後のロンドンは不況や治安悪化に揺れており、エディはその空気を象徴する「都市の亡霊」のようです。
サウンド面については、テンポの速さやラフなサウンドから、「パンク的」と評されることも多いのですが、バンドメンバーは“俺たちはパンクじゃない。70年代のハードロックやプログレッシブ・ロックから影響を受けている”と明言しています。
実際、本作の随所には組曲的な展開や緻密な構築性が体現されており、その作風は批評家からも広く認められてきました。
結果として、本作は“パンクの即効性”と“プログレッシブ的構築美”を同時に表現した作品として位置づけられ、NWOBHMの幕開けを告げる代表的名盤となったのです。
スピード感や荒い録音、そして吐き捨てるようなボーカルスタイルがパンク的に聴こえる要因です。ただし実際には、ツイン・ギターの対位法や組曲的展開など高い構築性を持っており、シンプルなパンクとは本質的に異なる音楽性です。
Iron Maidenのエピソード
1980年4月、アイアン・メイデンはデビューアルバムIron MaidenをEMIからリリースしました。本作はバンドにとって初のフル・アルバムであり、同時代に勃興したNWOBHMの代表的作品として位置づけられています。
録音は1980年1月、ロンドンのキングスウェイ・スタジオで行われました。クレジット上のプロデューサーはウィル・マローンですが、実際の現場ではエンジニアのマーティン・レヴァンとメンバー自身が中心となって制作が進められました。
限られた予算と短い期間で仕上げられ、完成までに要したのはわずか数週間だったと伝えられています。当時のメンバーはスティーヴ・ハリス、ポール・ディアノ、デイヴ・マレー、デニス・ストラットン、クライヴ・バーの5人でした。
収録曲の『Running Free』や『Phantom of the Opera』はバンドの方向性を明確に示すナンバーとなり、一方で『Sanctuary』は当初英国盤に含まれずシングルとして発表され、後に北米盤LPに収録されました。
ジャケットにはデレク・リッグスによる骸骨的キャラクター「エディ」が初登場し、以後バンドの象徴として描かれ続けます。
アルバムは全英チャートで最高4位を記録。シングル『Running Free』は34位、『Sanctuary』は29位にランクインしました。また、BBCの音楽番組『Top of the Pops』では『Running Free』を生演奏で披露し、リップ・シンクが慣例であった同番組で異例の扱いとなりました。
リップシンクとは、あらかじめ録音された音源に合わせて口の動きや歌唱のふりを行うことで、実際にはその場で歌唱をしていない状態のことです。
リリース後にはジューダス・プリーストやKISSのツアーに帯同し、活動規模を拡大していきます。世間的な評価としては録音の粗さを指摘する声があるものの、新しいメタルの到来を告げる作品として高く評価され、後年のランキングでも繰り返し取り上げられています。
Iron Maidenの収録曲
- Prowler
- Remember Tomorrow
- Running Free
- Phantom of the Opera
- Transylvania
- Strange World
- Charlotte the Harlot
- Iron Maiden
Sanctuaryは1980年にシングルとして発表された楽曲で、当初のUK盤Iron Maidenには未収録でした。北米盤や1998年リマスター盤では収録されましたが、2015年以降の再発では除外されており、現在の配信サービスでもスタジオ版は聴くことができません。そのため、現在では入手が難しい音源となっています。
PickUp:Prowler
アルバムの幕開けを飾る『Prowler』は、アイアン・メイデンの初期衝動を象徴する1 曲です。イントロから響くスティーヴ・ハリスのベースライン、鋭いギターのリフ、そしてポール・ディアノの荒々しい声が、当時のストリートに漂う空気感を描いています。
歌詞は“徘徊者(Prowler)”を題材に、都会の裏路地で女を物色する不穏な男の姿。
性的な欲望と暴力的衝動が交錯するその世界には装飾的な表現はなく、むき出しの視点で描かれているのが特徴です。美化とは無縁の生々しさであり、1980年前後のロンドンの現実とも重なって見えます。
サウンド的には、スピード感を基調にしつつ、ツインギターの短い掛け合いやブレイクが組み込まれており、後の大作志向へとつながる構築性がすでに現れています。デビュー作の冒頭に配置されたことによって、バンドの方向性を鮮明に示す役割を果たしています。
PickUp:Phantom of the Opera
アルバムの中心を担う『Phantom of the Opera』は、初期アイアン・メイデンの代表曲として知られる大作です。7分を超える長尺の中に複数の展開を組み込み、当時のNWOBHMの新人バンドとしては異例の構築性を描いています。
歌詞はガストン・ルルーの小説『オペラ座の怪人』に着想を得た内容です。
舞台裏に潜む怪人の存在と、その狂気と哀しみが交錯する物語。陰影に富んだ視点で描かれた歌詞は、初期のストリート感覚を持ちながらも文学的な広がりを見せています。
サウンド面では、疾走するハリスのベースに乗せてツインギターが対位法的に絡み合い、緩急の切り替えによって短い組曲のように展開していきます。
中間部には長いインストゥルメンタルが置かれ、ギターの旋律とベースラインが交差しながら曲全体を推進する構成。デビュー作にして、後の大作志向を決定づけたナンバーです。
おすすめの聴きかた
Iron Maidenはアルバム1枚で完結している名盤です。聴くときには1曲目からラストまで「通し」で聴くことをお勧めします。歴史的名盤のほとんどは、アルバム単位で作品が完結しており、映画を観るように「通し」で聴くのが基本です。
この作品は録音の粗さと演奏の勢いがそのまま記録されているアルバムです。ラフな音像の中で、疾走するベースやギターの掛け合いが交差するサウンドが大きな魅力です。
AirPods(Pro)のような優しい音質では表現しきれない作品と思いますので、音圧や躍動感の強いリスニング環境で聴きましょう。
あとがき(Iron Maiden)
わたしがNWOBHMを聴きはじめた頃に出会ったのがアイアン・メイデンでした。
まだロックを聴き込んで間もない時期でしたが、その音には理屈を超えた「純粋なロック」を感じ取ったのを覚えています。
RainbowやBlack Sabbathのような格調高い様式美とは、どこか異なる感覚。美しさよりも荒々しさが前面にあり、バンド自身は否定しているものの、やはり当時の“パンク”の衝動を秘めているように感じられました。
そして、サウンドの土台であるベースを担うスティーヴ・ハリスが、作詞作曲の多くを手がけている点も印象的でした。ベーシストがここまで前面に立って音楽を形づくるバンドは決して多くはなく、その姿勢が作品の世界観を描いているのだと思います。
さらに、本作はブルース・ディッキンソンが加入する以前、初期ボーカルのポール・ディアノによる歌唱で制作されている貴重な作品。
あなたにとっても「聴き継がれるアルバム」になれば嬉しいです。