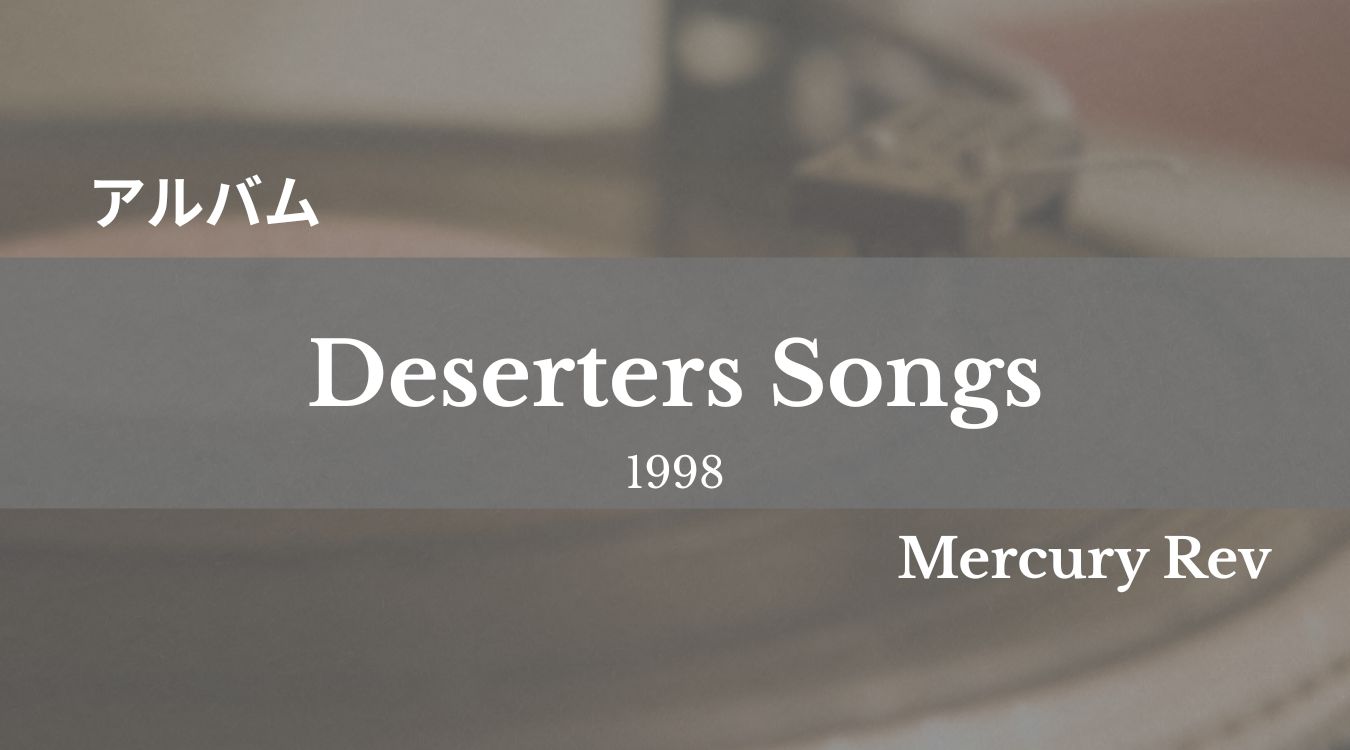当サイトの評価
[★★★★(MAX)]
- 4thアルバム
- リリース_1998年
- 作品名_Deserter’s Songs
Spotify
Apple Music
静寂の中にある絶対的な美の残響
本作Deserter’s Songsは、米国のオルタナティブ・ロックバンド、マーキュリー・レヴの4thアルバムです。
同バンドは、これまでに3枚のアルバムを発表してきましたが、いずれも商業的には振るわず、一般的な認知は高くありませんでした。それは、当時の音楽シーンの主流に迎合せず、商業的成功よりも自己表現を優先した結果でもあります。
彼らはノイズやサイケデリア、そして管弦楽的アレンジを融合させ、幻想的な音響世界を築いてきました。しかし、その複雑な構成や感情の抽象性は、リスナーにとって決して容易なものではありませんでした。
そして、メンバーの脱退と崩壊寸前の状況を経て制作されたのが本作Deserter’s Songsです。
依然として大衆受けを意識することなく、“自分たちの音楽”を徹底的に追求して完成させたこのアルバムは、前3作で模索し続けた“絶対的な美”を内に秘めています。
ボーカルの旋律ではなく、音響全体で世界観を描くというマーキュリー・レヴの根源的な音楽性は変わりません。ただし、バンドのサウンドを象徴していた“ノイズ”を削ぎ落とし、より映画的で空間的な作品へと昇華しました。
ギターの轟音やノイズは最小限化。代わってストリングスと管楽器、そして微かなピアノの響きが、夜の空気に溶けるように漂います。
このアルバムの美しさは、旋律の華やかさではなく、空間の中に共鳴する“音の粒”にあります。
メロディが楽曲を主導するのではなく、一音一音が空間の中で共鳴し合い、静かな残響を残す。聴く者を現実から少し離れた世界へ導いていきます。
宇宙や時空の揺らぎ。星と星のあいだに広がる真空のような静寂感。そこに、本作の“絶対的な美”が宿っています。
Deserter’s Songsのエピソード
本作Deserter’s Songsは、1998年にV2レコードからリリースされました。
それまで在籍していたメジャーレーベルを離れ、非メジャーな体制で再出発を果たした作品です。制作の中心を担ったのは、フロントマンのジョナサン・ドナヒューと、プロデューサー/エンジニアのデイヴ・フリッドマン。
彼らはニューヨーク州キャッツキル山地にある小さな個人スタジオで、長い冬のあいだ静かに録音を重ねました。
3rdアルバム『See You on the Other Side』の商業的失敗を機に、バンドは深刻な混乱期を迎えていました。メンバーの脱退や内部不和、実質的なメジャー・レーベル契約の終了。
ツアーも続けられず、グループとしての存続が危ぶまれる状態にまで追い込まれます。
“I was thinking, ‘Well, OK… I’ve got to go out there and pump gas for the rest of my life.”
(僕は「そうか、もうこの先は一生ガソリンスタンドで働くのかもしれないな」と思っていた)
出典:Jonathan Donahue, The Quietus(May 23, 2011)
ジョナサンは精神的にも限界に達し、「これが最後のアルバムになると思っていた」と語っています。本作の制作は、彼にとって“再生”というよりも、“終わりのための祈り”に近いものでした。
録音は低予算のもとで行われましたが、フリッドマンの手によって音響は驚くほど豊かに仕上げられました。ギターの轟音やロック的衝動は姿を消し、代わりにストリングス、ホルン、フルート、ピアノが静かに配置されていきます。
それぞれの音が空間に散り、やがて静寂の中へと溶けていく。崩壊を受け入れながら、なお美の核心に手を伸ばそうとするアーティスト性。
「自分たちのためだけに作った」と語られるこのアルバムは、完成後に予想を超える反響を呼びます。
Deserter’s Songsは英国でゴールドディスクを獲得し、世界的評価を受けると同時に、崩壊寸前だったバンドに再び生命を与えたのです。
結果的に、“終わりを告げるための作品”が、“再生の始まり”となりました。
“I thought Deserter’s Songs would be the last record we ever made.”
(『Deserter’s Songs』が、僕たちの最後のアルバムになると思っていた。)
出典:Jonathan Donahue, Mojo Magazine(2008)
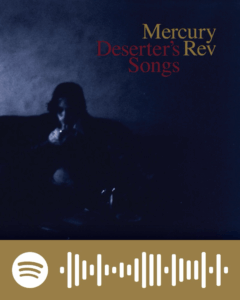
Deserter’s Songsの収録曲
- Holes
- Tonite It Shows
- Endlessly
- I Collect Coins
- Opus 40
- Hudson Line
- The Happy End (The Drunk Room)
- Goddess on a Hiway
- The Funny Bird
- Pick Up If You’re There
- Delta Sun Bottleneck Stomp
『Deserter’s』とは脱走兵や義務を放棄した者に使われる単語。本作のアルバム・タイトルは「夢を放棄した」や「音楽から逃げた」など、自嘲と自己喪失のニュアンスを含んでいるようです。
PickUp:Holes
本作のオープニングナンバー『Holes』。
歌詞は存在しますが抽象的かつ詩的のため、アーティストの意図を正確に解説することができません。
しかし、本作Deserter’s Songs自体、バンドのフロントマンであるジョナサン自身が「終わりのための祈り」と語ったことから、夢に届かなかった、手が届かない理想、という喪失と無力感が描かれていることは間違いないでしょう。
サウンド面では、木管やストリングス、ホルンなどの柔らかいアンサンブルが、夜の静寂の中でゆっくりと広がっていきます。ギターの轟音や歪みはほとんど姿を消し、代わりにピアノとフルートが淡い光のように散りばめられ、オーケストラとアンビエントの境界を浮遊するような音響が続きます。
曲全体にリズムの起伏はほとんどなく、呼吸のように穏やかに進行します。そこには、「最後の希望」という光ではなく、崩壊を受け入れたあとに残る静かな余韻が漂っています。
“That big blue open sea, That can’t be crossed, That can’t be climbed”
“Just born between”
(あの大きな青い開けた海、渡ることができない海、登ることができない海)
(ただそのあいだに生まれた)
出典:Mercury Rev『Deserter’s Songs』(1998, V2 Records)
PickUp:Goddess on a Hiway
本作Deserter’s Songsの夢想的な楽曲の中でも、一際、美しさを誇る『Goddess on a Hiway』。
どのようなバラードの名曲を並べても、この楽曲を通じて形成される“情感”は再現できないと思います。それは旋律や構成といった音楽的要素ではなく、ひとつひとつの音の奇跡的な調合、と表現するほかありません。
この曲は、ジョナサン・ドナヒューが1980年代末に書いた未発表のデモ・トラックが基になっており、アルバム制作時にカセットテープで発見され再録されたと言われています。
歌詞世界は、やはり抽象的なため、正確な意図は読み取れませんが、登場する“女神”は恋人ではなく「夢・理想」を表しているように思えます。
楽曲は、短い間隔で何度もサビをくり返しますが、それが単調ではなく“感情の波”のように設計されており、1曲の中で、同じ響き方に感じさせません。
サビのあとに続くベースの無常感、旋律ではなく効果音としてのピアノ。宇宙の浮遊感を表現するかのような繊細に散りばめられた音。
すべてがこの楽曲の美しさを際立たせています。
“And I know it ain’t gonna last”
“And I know it ain’t gonna last”
“And I know it ain’t gonna last”
(分かっている。これは長くは続かない※くり返し)
出典:Mercury Rev『Deserter’s Songs』(1998, V2 Records)
おすすめの聴きかた
Deserter’s Songsはアルバム1枚で完結している名盤です。聴くときには1曲目からラストまで「通し」で聴くことをお勧めします。歴史的名盤のほとんどは、アルバム単位で作品が完結しており、映画を観るように「通し」で聴くのが基本です。
そして本作は、空間の中で響く音の粒や、空間全体の揺らぎまでを感じ取ることで、その真価が現れる作品です。屋外よりも、照明を控えた落ち着いた部屋で、そして就寝前などの心が静まった時間に聴くことをおすすめします。
また、イヤホンやヘッドホンで聴くことで、立体的に広がる音の動き、わずかな残響の変化までも感じ取ることができます。このアルバムは、音の厚みではなく音響空間そのものを聴く作品です。
あとがき(Deserter’s Songs)
これが最後のアルバム
そのような思いで制作された本作Deserter’s Songsは、ついにマーキュリー・レヴの音楽がリスナーに広く共鳴し、高い評価を受ける作品となりました。
彼らはこれまでも一貫して、商業性よりも“自分たちの音楽”を追求してきました。しかし、メジャーレーベルと契約を続け、音楽を広く聴いてもらうためには、どうしても一定の成功が求められます。
何がきっかけで本作が広く受け入れられたのか、理由は分かりません。しかし、当時のアーティストの心情や制作環境、そして定義できない“何か”が作用した結果、名だたる名盤にも比肩する作品が生まれました。
もし彼らが、「次作は絶対に売れるアルバムを作ろう」と“ポジティブに”取り組んでいれば、この名盤は存在しなかったでしょう。
ボーカルのジョナサンは、大きな特徴を持たない乾いた声質ですが、その「非・表現性」は、Deserter’s Songsの静謐な音響と完璧に呼応しています。
このアルバムの美しさを説明するのが難しいように、世の中には言語化できない感想があります。あえて言葉にするなら、それは『芸術』なのかもしれません。
本作Deserter’s Songsが、あなたにとっても「聴き継がれるアルバム」になれば嬉しいです。
“We went into Deserter’s Songs … quite realistically thinking this is the last thing we are ever going to do. We were sure that nobody would hear it, that nobody wanted a Mercury Rev record.”
(Deserter’s Songsに入るとき、かなり現実的に“これが僕たちが最後にやることだ”と思っていた。誰にも聴かれないだろう、誰もマーキュリー・レヴのレコードを求めていないだろうって確信していたんだ。)
出典:Jonathan Donahue, The Big Takeover(Interview, Part I, 2011)