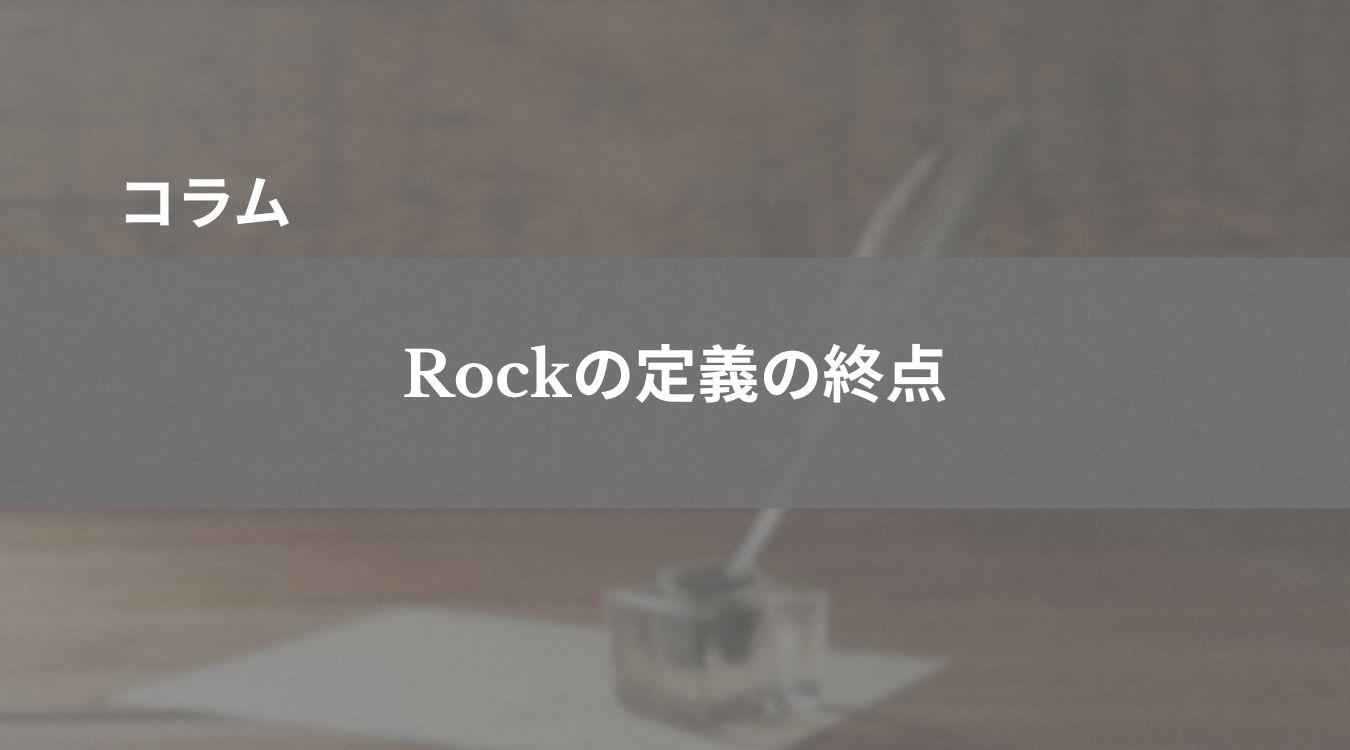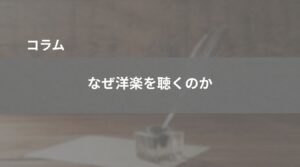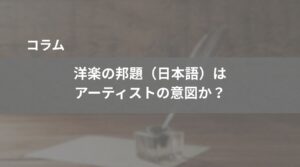ロックとは何か(ロックの定義)
「ロックとは何か」と問うとき、明確な定義を与えるのは困難です。
なぜなら、演奏スタイル、音の構造、歌詞、社会的背景など、あまりに多くの要素が絡み合っているから。たとえば、ギターは象徴的ですが、なくてもロック的であり得ます。激しさもあれば静けさもある。
つまり、定義に必要と思われる要素のどれを欠いても、なお“ロックらしさ”が残ってしまいます。
この曖昧さは、「ジャンルとは何か」という根本的な問いに接続されます。ジャンルは分類であり、制度であり、秩序です。
一方、ロックはもともと、その秩序に抗う衝動として生まれています。ゆえに、ロックを制度的に定義しようとする行為は、皮肉にもロック性を失わせる作用を持つのです。
定義しようとした瞬間に画一化され、ロックはロックでなくなる。
それが、このジャンルの抱える矛盾であり、魅力でもあります。
ロックの大衆的定義(大衆的分類欲望)
ロックが「ジャンル」として強固に制度化された背景には、人々の「分類したい」という根源的な欲望があります。
人は自分が聴いている音楽を分類したいと望む。それは、音楽を消費する自分自身にも、何らかの“属性”を付与したいからです。
Spotifyやレコード店で「ロック」という分類に収まることは、音楽だけでなく、自分の立ち位置を定める行為でもあります。
こうしてロックは、「エレキギター」「バンド編成」「叫ぶ」「不良っぽさ」など、視覚や音響で認識しやすいイメージによって定義されてきました。
しかし、それらの要素はすべて後から貼られたラベルにすぎません。 ロックが生まれた当初、それは「ロックをやろう」として始まったものではありませんでした。
名付けられる以前のロックには、分類される意図も形式も存在しなかったのです。
ロックの主観的定義(ロックの根源性)
一般的に“ロック”と呼ばれてきた音楽が、必ずしも自分にとってロックとは感じられない。なぜ“Livin‘ on a Prayer”にロックを感じず、“Let it be”にロックを感じるのか──
そんな違和感を抱いてきたことに、最近ようやく自覚的になりました。
ロックを感じないロック、そして感じるロック。
改めてアルバムを聴き比べると、ひとつの傾向が見えてきました。
私は、アーティストの“内的衝動性”のようなものが主軸になっている作品からロックを感じていたのです。内側の感情をさらけ出し、“音楽”という手段で見事に表現した作品に宿る“内的衝動”。
それは、激しいものと限定されず、狂気性や美しさでも成立する。
一方で、ロック的でありながらキャッチーさと外面的な魅力を優先したようなサウンドには宿らないのだと思います。
たとえば、ケイト・ブッシュの『Wuthering Heights』。あの曲にはギターリフも叫び声もありません。
それでも私は、そこにロックを感じた。あの音には彼女自身の衝動が宿り、聴き手に異物感として突き刺さってくる。
“内的衝動性”を言語化するのは難しいです。表面上の語りかけと本心からの語りかけの区別を、言語で説明するのが難しいように。
ただし、単純に売名や成功を目指すような戦略的動機ではない“衝動性”が存在する。
それが、私にとって“ロックの定義”だったのです。
これならば、B’zの楽曲にロックを感じず、尾崎豊の『卒業』にロックを感じる私自身の感性も説明できます。
バラード曲はロックになり得るか(内的衝動性の限界)
内的衝動性
これをロックの主観的定義としても、本題の結論にはなりません。“内的衝動性”だけを基準にした場合、次のような論理が成立しうるからです。
- 失恋経験に基づき内的衝動性から描かれたバラードはロックである
- セールスや評価への願望が内的衝動よりも前面に出た音楽はロックではない
- ロック以外のジャンルに属する楽曲は内的衝動性を含まない
たしかに、内面から発生したような音には、形式を問わず惹きつけられるものがありますが、そこにロックを感じるかどうかは、また別の問題です。
どれほどの情熱がこもっていようとアコースティックに歌われたバラード曲や音楽家の内的衝動が再現されたクラシックの名演奏をロックとして分類してよいのか。
この違和感は、ロックという現象が、内的衝動だけでは決まらないことを意味しています。
そして同時に、ロックは客観的な様式やジャンルではなく、最終的には聴き手の感性が“意味付け”しているのかもしれません。
つまり、音楽そのものが、どのようにして私たちの中に“現れる”のか、という構造に目を向ける必要があるのです。
音楽は認識するから存在する(音楽の発生構造)
「音楽」という言葉は、実体を指していません。
それは可視化できる対象でも、物質でもなく、意味のない波が知覚され、意味を持つプロセスそのものを指しています。
たとえば、CDやストリーミングの音源データ。それ自体は音楽ではありません。それは、まだ意味のタグを持たない“構造物”にすぎない。
音楽は、それを聴く身体が介在した瞬間に初めて現れます。
音そのものには、「切なさ」も「怒り」も「ロック性」も含まれていません。あるのは、ただの波動、数理的な構造だけ。
人間はそれを、経験や感性で受け止め、既知の枠組みに照らして意味付けします。そう、洋楽の歌詞の意味を知った途端、楽曲の印象が変わるように。
この時点で音楽はようやく、現象として“存在し得る”のです。
音楽とは、「再生 × 知覚 × 意味化」によってリアルタイムで生成される現象。
言い換えれば、保存も再現もされていません。音楽は“保存”されているように見えますが、それはただの物理的な記録であり、現象としての音楽は一度きりの知覚経験でしか成立しないのです。
この構造は、ロックという現象にも当てはまります。
私たちは音楽の中に「ロック的である何か」を感じます。しかし、それは楽曲の形式や評価軸ではなく、聴き手の知覚のなかで立ち上がる“感覚のタグ”によって初めて成立するもの。
だから、ケイト・ブッシュもクラフトワークもトム・ヨークも、ジャンルの外側から“ロック”として感じられるのです。
ロックとは画一的なジャンルではなく、意味生成の構造的体験のこと。「それがロックである」と感じられた瞬間だけに、ロックという現象は発生するのです。
聴き手ごとに。
終点(ロックの定義不能性)
音楽とは、記録でも演奏でもなく、人がそれを感じた瞬間にだけ立ち上がる意味の現象のこと。データや形式ではなく、知覚の中に意味が発生するとき、はじめて音楽は存在するのです。
昨日感じたロックが、今日は感じられないかもしれない。
この視点に立ったとき、「ロックとはなにか」という問いも、制度的な定義やジャンルによって語ることが困難になります。ロックは客観的に存在するものではなく、それがロックだと感じられた瞬間にだけ存在するものだから。
実際、過去には多くのアーティストたちが“ロックに憧れ”、あるいは“ロックを名乗って”音楽を表現してきました。たとえそれが制度化された模倣であったとしても、それを聴いた誰かが「ロックだ」と感じたのであれば、その瞬間にロックは確かに存在していたことになります。
つまりロックとは、様式ではなく、意味が発火する構造そのもの。 それが制度の中にあろうと外にあろうと、“人の知覚を通じて発生する”という一点において、ロックは常に定義不能であることを前提としながらも、確かに存在し続けるのです。
音楽理論の観点では、ロックは、4/4拍子を基調とし、エレキギター主導のバンド編成を用い、ペンタトニックスケールやブルース由来のシンプルなコード進行を土台とするリズム主導型。
このように形式化することで一定の定義は可能です。
こうした分析は、ロックの音楽的構造を理解するうえで有効ですが、その本質──感情の発火や文化的意味性──には届きません。
ロックとは形式ではなく、知覚と意味を通じて発生する体験的な現象なのです。