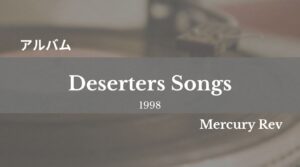当サイトの評価
[★☆☆☆]
- 2ndアルバム
- リリース_1983年
- 作品名_Shout at The Devil
Spotify
Apple Music
猥雑さをサウンドにしたような“非メタル”作品
1983年、モトリー・クルーは2ndアルバムShout at the Devilをリリースしました。
1stで見せたストリップ文化の享楽性と危険の美学を、そのまま巨大なエンターテインメント・ショーへと昇華させた作品です。このアルバムで、モトリー・クルーが持つストリートの不良性をさらに過激に押し広げました。
サウンド面では、前作のデビュー時の衝動をよりヘヴィに表現。快楽や暴力、さらに“悪魔”といったテーマを混在させた世界観を描いており、「Rock=ワル」の公式を証明したかのようなアルバムです。
当時のロサンゼルスでは、ストリップやクラブ文化がロックと密接に結びつき、“危険”や“退廃”といった言葉がファッションの一部として消費されていました。モトリー・クルーはその空気を象徴する存在であり、本作Shout at the Devilではそれを音・映像・イメージのすべてで猥雑に再構成しています。
アルバム全体から漂うのは、思想ではなく本能、純粋な不良性。
一方、多くの批評メディアで書かれているような“メタル感”は、少なくともサウンドには帯びていません。正当なメタルではなく、「ハードロック」に分類されます。
『メタル』という音楽用語は、本来、硬質で構築的な音響。さらに、神話的、反宗教的、超越的なテーマを持つ音楽に使われてきました。しかし、いつしか「メタル」は商業的な“ラベル”と化し、外見的要素でもラベリングされるようになりました。
モトリー・クルーはハードロックの系譜に位置し、音響的にはメタルの要素をほとんど持ちません。
Shout at The Devilのエピソード
1983年9月、モトリー・クルーは2ndアルバムShout at the Devilをリリースしました。
デビュー作『Too Fast for Love』の成功を受けてエレクトラ・レコードと契約し、制作体制を刷新。プロデューサーにはチープ・トリックなどを手がけたTom Wermanを迎え、ロサンゼルスのチェロキー・スタジオで約2か月にわたりレコーディングが行われました。
1st『Too Fast for Love』が低予算・短期間で録られたアンダーグラウンド作品だったのに対し、本作では大規模な予算が投入され、レコーディング機材やミキシング環境も格段に向上しました。
つまりこの作品は、モトリー・クルーが“アンダーグラウンドの危険”をメジャー資本のもとで再現したアルバムでもあります。
当時のアメリカでは、宗教右派が過激なRockを「悪魔崇拝」と非難し、“サタニック・パニック”と呼ばれる社会現象が起こっていました。モトリー・クルーはその空気を逆手に取り、アルバムタイトル自体を挑発の対象にしたのです。
“Shout at the Devil”――「悪魔に向かって叫べ」というこの言葉は、崇拝ではなく反抗を意味しています。彼らは、世間の恐怖と偏見を最大のマーケティング要素として利用しました。
リリース後、本作は当然のように賛否両論を巻き起こしますが、全米チャート17位を記録し、バンド初のプラチナディスクを獲得。炎・革・血糊・逆十字といった過剰な演出も批判を集めながら、それ自体がMTV時代の象徴になりました。
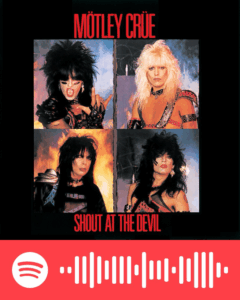
Shout at The Devilの収録曲
- In The Beginning
- Shout At The Devil
- Looks That Kill
- Bastard
- God Bless The Children of the Beast
- Helter Skelter
- Red Hot
- Too Young To Fall In Love
- Knock ‘Em Dead, Kid
- Ten Seconds To Love
- Danger
PickUp:Shout At The Devil
アルバムの幕開けを飾るタイトル曲であり、モトリー・クルーを象徴する代表曲。ヘヴィメタルというよりも、反逆をエンターテインメントとして成立させた“時代の呪文”のような楽曲です。
冒頭の「Shout, shout, shout――」という連呼は、宗教的呪文のように響きますが、その実態は“悪魔に屈するな”という反抗のメッセージ。当時の“サタニック・パニック”を背景に、モトリー・クルーは“悪魔”という概念を挑発の象徴として使い、大衆の恐怖を逆手に取ったマーケティングを完成させました。
サウンド面では、ミック・マーズのギターが作り出す粘着質な歪みと厚みのあるリフを主軸にし、トミー・リーのドラムは硬質なリズムを維持。楽曲全体に異様な緊張感を与えています。
歌詞は、誘惑・暴力・嘘・裏切りといった人間の暗部を“悪魔”として象徴的に描いており、その悪魔像は外在的存在ではなく、人間の内部に潜む破壊衝動を指しています。
「悪魔に向かって叫べ」とは、己の中の破滅と向き合うという意味での反抗であり、このメッセージがアルバム全体を貫く精神的な軸となっています。
PickUp:Helter Skelter
ビートルズの名曲をカバーした1曲。モトリー・クルー版『Helter Skelter』は原曲の文脈を完全に破壊し、80年代的暴力と享楽の象徴として再構築されています。
原曲はポール・マッカートニーが“ロック史上初のヘヴィチューン”を狙って制作したものでしたが、モトリー・クルーはそれをさらに過剰化し、スピードと歪みの奔流として提示しました。
ギターのリフは粗く歪み、ドラムは肉感的に響き、全体が混沌の中で蠢くような迫力を持っています。
このカバーは単なる敬意ではなく、純粋な“ロックの再占拠”。つまり、英国のロックが築いた伝統を、アメリカ西海岸のストリップ文化と結合させ、ビートルズが表現し得なかった“汚れた快楽”へと転化しているのです。
歌詞の内容自体は変わっていないものの、ヴィンス・ニールのハイテンションなシャウトが、原曲の遊戯性を完全に上書き。そこに残るのは、歓楽街の喧騒と暴力をそのまま音にしたような混沌です。
原曲のリリースから15年後、“米国のワルのバンド”によって再演された『Helter Skelter』は、ロックの原点を猥雑な現代へ引きずり戻したカバー曲。
おすすめの聴きかた
Shout at The Devilはアルバム1枚で完結している名盤です。聴くときには1曲目からラストまで「通し」で聴くことをお勧めします。歴史的名盤のほとんどは、アルバム単位で作品が完結しており、映画を観るように「通し」で聴くのが基本です。
本作は、モトリー・クルーの危険さと衝動をメジャーレーベルの環境で録音したアルバム。レコーディング機材やミキシング環境も格段に向上した環境で制作されています。また、音楽性そのものよりも、演出性が際立つ作品です。
AirPods(Pro)のような優しい音質では表現しきれない作品と思いますので、音圧や躍動感の強いリスニング環境で聴きましょう。
あとがき(Shout at The Devil )
洋楽Rockを聴き始めた10代後半、本作Shout at The Devilはわたしの愛聴盤でした。
当時はその危険な雰囲気や反抗的なイメージに惹かれ、「Rockとはこういうものなのか」と胸を高鳴らせたのを覚えています。
しかし、聴く音楽の幅が広がり、Rockをより深く味わうようになるにつれて、再生する機会は少なくなりました。それでも、この作品が“Rockの入り口”として持つ力は今も変わりません。
初めて洋楽Rockに触れる人にとっては、「ワル」の世界に足を踏み入れるようなドキドキ感を味わえる一枚だと思います。危険と享楽、そして80年代の空気がすべて詰まったアルバム。
Rockという言葉が持つ一般的なイメージ、“派手さ、反抗、不良性”を最も分かりやすい形で体感できる作品です。
あなたにとってもお気に入りの1枚になれば嬉しいです。