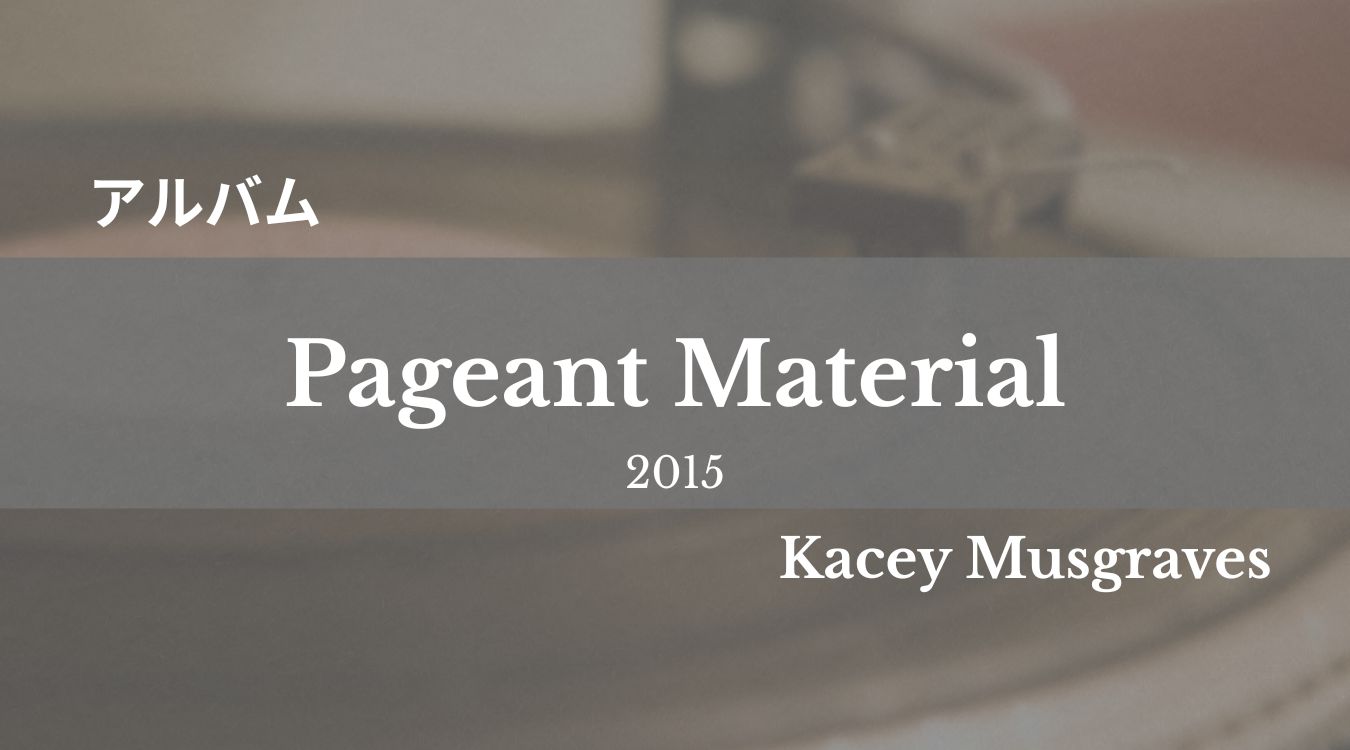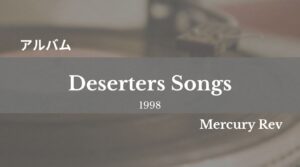当サイトの評価
[★★★★(MAX)]
- 2ndアルバム
- リリース_2015年
- 作品名_Pageant Material
Spotify
Apple Music
「自分らしさ」を描いたカントリーの新たな名盤
本作Pageant Materialは、ケイシー・マスグレイヴスの2ndアルバムです。
デビュー作『Same Trailer Different Park』の成功を、プレッシャーではなく、ポジティブに堂々と受け止めたような雰囲気を帯びており、自然体を大切にする彼女らしさが伝わってきます。
前作と同様、過剰な演出を排した等身大の作風ですが、本作ではそれがより自由でポップに展開されており、伝統的なカントリーを基盤にしながら、ケイシーらしい皮肉や風刺が自然体のまま表れています。
全体として、明るさと軽やかさにあふれ、音楽創作を楽しむ姿勢が素直に伝わってくる作品。
また、いくつかの楽曲からは、ロックのような快感も感じ取れます。
『Late to the Party』のリフの反復が生み出す気持ちよさ、『Biscuits』の後半に感じる展開と“聴感上のドラマ性”には、ロックの構造と共鳴するような高揚感があります。どちらもジャンルを越えた“聴いていて気持ちのいい瞬間”が存在します。
ロックのような“衝動性”とは異なる、清涼飲料水が身体に浸透するような心地よさ。
本作は、海外のさまざまな主要メディアで高評価を得ていますが、「ロック的」と評されている事実はありません。この記事は、あくまでもわたしの主観性で書いています。
そして、収録曲はいずれもシングル・カットされても成立するほどの完成度を誇り、創作力が1stでピークを迎えたわけではないことを証明しています。
Pageant Materialは、「自分らしく」という彼女の姿勢が明快に表れた、カントリー・ミュージックの新たな名盤です。
Pageant Materialのエピソード
本作Pageant Materialは、デビュー作から2年後の2015年にリリースされました。
プロデューサー陣には前作と同じく、シェーン・マカナリーやルーク・レアードが名を連ねており、ナッシュビル録音の体制に大きな変更はありません。
本作のアルバムタイトルの“Pageant Material”とは、「ミスコン向きの人材」「品行方正で華やかな理想像」といった意味を持つ言葉です。
一方で、ケイシー・マスグレイヴスは「人に良く思われようとして本音を隠すのは好きじゃない」と公言しています。それはデビューアルバムの作風にも強く反映されている、偽りのない信条でしょう。
つまり本作は、自身の価値観と「理想的な女性像」との対比を、あえて“ミス・アメリカ”的な文脈で皮肉ったもの。
アルバムジャケットでも、ティアラやサッシュを身につけてミスコン風に着飾った自身を登場させることで、逆説的なメッセージを込めています。批判的に感じさせない、ユーモアに富んだ彼女らしい演出です。
リリース後、本作は全米アルバムチャートで初登場第3位を記録し、前作に続いて商業的成功を収めました。初週売上は約60,000枚で、カントリー・チャートでは1位を獲得しています。
また、Pageant Materialという挑発的なアルバムタイトルや、ドレスアップした本人が玉座に座るジャケットのビジュアルは、メディアでも大きな話題を呼び、ケイシー・マスグレイヴスのアイロニカルで一貫した作家性を印象づけました。
Pageant Materialの収録曲
- High Time
- Dime Store Cowgirl
- Late to the Party
- Pageant Material
- This Town
- Biscuits
- Somebody to Love
- Miserable
- Die Fun
- Family Is Family
- Good Ol’ Boys Club
- Cup of Tea
- Fine
- Are You Sure(feat. Willie Nelson)Hidden Track
PickUp:Biscuits
“他人をけなしても、自分の評価は上がらない”
“他人を小さく見せても、自分が大きくなるわけじゃない”
『Biscuits』は、他人を非難したり、他人の問題に口を出したところで、自分が優位に立てるわけではないという人生の真理を、軽妙な語り口で提示した楽曲です。そして、「自分のことで精一杯な人間が、なぜ他人を批判しているのか?」という、現代社会への問いかけでもあります。
これは、単なる道徳の押しつけではなく、「他人に構うより、自分の人生をきちんと整えた方が、物事はうまくいく」という、シンプルな人生訓です。
“自分のビスケットだけを思い描けば、人生はきっといい感じになるから”
サウンド面でも、バンジョーやアコースティック・ギター、軽快なスネアドラムのリズムなど、カントリーらしい正統派なアレンジが印象的。後半のスチールギターの間奏部では、ビート感と演出的な煌めきがロックンロールのような高揚感を感じさせます。
また、説教っぽさや押しつけがましさは一切なく、口語的なフレージングも彼女ならではの魅力です。
PickUp:Good Ol’ Boys Club
『Good Ol’ Boys Club(古き良き男子クラブ)』とは、アメリカにおける既得権益層や、男社会・内輪主義を揶揄する言葉です。
この楽曲の歌詞では、「そういう世界には入りたくない」と明確に宣言しています。
自分が積み上げてきた努力や実力は、いわゆる“会員証”や“推薦”といった業界的な承認によって証明されるものではない。そして、他人のやり方に合わせない姿勢と、自分に正直に生きることへの価値観が歌われています。
これは、音楽業界に限らず、あらゆる場所で目にする“忖度”や“派閥”といった社会構造そのものに対する反発ともいえるでしょう。ただし、攻撃的にはならず、あくまでウィットと皮肉で包みながら、柔らかく表現されているのが彼女らしいところです。
この曲のメロディは、不必要な起伏をつけない自然体の旋律構成が印象的。大げさな展開はないものの、気だるさを帯びたリズムの中に、淡々とした強さが秘められています。
そして、どこか懐かしさや哀愁を感じさせる不思議な魅力もあります。
過剰に演出せずに本音を語るスタイルが、アルバム全体のテーマ性に通じる1曲。
“Another gear in a big machine don’t sound like fun to me”
“I don’t wanna be part of the good ol’ boys club”
(機械の歯車になるのは楽しそうじゃないから)
(古き良きボーイズクラブなんて入りたくない)
出典:Kacey Musgraves『Pageant Material』(2015, Mercury Nashville)
おすすめの聴きかた
Pageant Materialはアルバム1枚で完結している名盤です。聴くときには1曲目からラストまで「通し」で聴くことをお勧めします。歴史的名盤のほとんどは、アルバム単位で作品が完結しており、映画を観るように「通し」で聴くのが基本です。
本作はデビュー作に続いて、どの曲もシングルとして成立するほどの魅力を持っています。PickUpで取り上げた曲だけでなく、ぜひアルバム全体を通して聴いてみてください。
なお、一般的なロックのように音圧や躍動感を重視したリスニング環境でなくても、十分に作品の本質を感じることができると思います。
あとがき(Pageant Material)
本作Pagent Materialは、タイトルやアルバムジャケットが表現する通り、世間の常識や基準を軽やかに皮肉って、「自分らしさ」に最大の価値を置くことをテーマにした作品です。
普段、わたしは音楽を聴く際に“歌詞”を重要視しませんが、本作の歌詞は作品テーマと強く関わっており、アルバムをより楽しめる要素と思いますので、この記事の最後に抜粋して紹介します。
2曲目:Dime Store Cowgirl
成功しても有名になっても、私は出身地の小さな町の少女(カウ・ガール)のまま──という自己宣言。豪華なものより、馴染みのある風景や人との関係を大切にすることを歌っています。
3曲目:Late to the Party
華やかなパーティーに遅れても気にしない。大切なのは時間を共有する人がそばにいること。社交の場や形式的な盛り上がりよりも、特別な相手と過ごす時間の価値を歌っています。
素朴なハイトーンのヴォーカルが美しく、当記事では、最後までPickUp選曲に迷ったナンバーでもあります。
4曲目:Pageant Material
「コンテストで映える華やかさや、求められる型に合わせることはできない」という開き直り。誰かの理想像に従うのではなく、自分自身であることを誇る姿勢を描いています。本作のタイトルナンバー。
10曲目:Family is Family
家族は愛すべき存在である一方で、時に面倒でもあるという関係性を、ユーモアを交えて軽やかに描いています。欠点も問題もたくさんあるが、それでも家族であることに変わりはない、と歌います。
12曲目:Cup of Tea
誰からも好かれる人になんかなれない。甘い紅茶が好きな人がいれば、苦いものが好きな人もいる。“みんなの紅茶”にはなれっこないなら、自分の好きなようにしたほうがいい、と歌った楽曲です。
どの楽曲も、ケイシー・マスグレイヴスさが感じられる人間味ある温かな世界が描かれたPagent Material。聴いていて、こんなに心地よさを感じるアルバムはそう多くありません。
あなたにとっても「聴き継がれるアルバム」になれば嬉しいです。